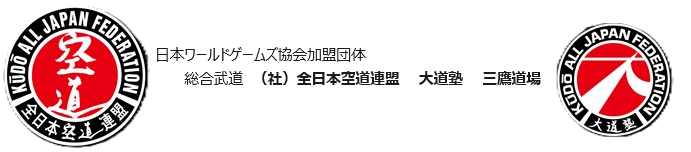”最先端の総合武道” 空道 大道塾三鷹同好会/Team Tiger Hawk Tokyoの小野です。
「食」テーマの2回目です。
各論に入る前に、前提としておきたいことに、今回は触れておきます。
「食」リテラシーの重要なわけ
なんでアスリートに栄養学をベースとした「食」の情報に対する理解力(リテラシー)が必要となるのか?
私見ですが、ふたつあると思っています。
ひとつは、競技において結果を出すべく、最高のコンディションを作るため。
もうひとつは、競技を辞めた後にも健康的に生きていくためです。
これはアスリート以外にも言えますね。
いわんや、ゆるアスにおいてをや、です。
強くなるだけじゃなく、毎年気になる健康診断の結果の改善のためにも(笑)、必要ですよね。
いろんないわゆる〇〇ダイエットが流行ったり廃ったりする中で、最低限の知識と判断力がないと騙されちゃいますよ、というのもありますし。
また、これも完全に個人的感覚ですが、日本においてはスポーツでも種目により温度差が大きいなと思っています。
栄養学的な知識の浸透度が高いのは、陸上競技・テニス・ボディビルディングなど。
逆に低いのは、野球、ラグビーや格闘技かなと。
低い、と自分の種目を書いてしまいましたが(笑)、個人として栄養学について調べて実践する人は相当数います。
ただ、共有されていないのかなと。
このブログが、共有の一助になればいいと思います。
そして、そうは言っても小野はスポーツ栄養学の専門家ではありませんので、あくまでも「自分たちで理解して考える」ためのきっかけになればとも思っています。
エディー・ジョーンズかく語りき
一方、低い印象があると書いたラグビーについて、最近の情勢を少し。
前日本代表ヘッドコーチ、エディ・ジョーンズ氏が、こんなことを言っています。
2014年のHC就任当時、キャプテンだった菊谷崇選手に話を聴いた時のこと。
「最初、彼の顔をパッと見て、太り過ぎていると思いました。(略)それは食事の問題だと私はアドバイスしました。それから6か月、彼はしっかりとしてトレーニングをし、食事を意識することで筋肉の量を5~6キロ増やすことに成功したんです。ただ、そのとき菊谷はすでに33歳になっていた。もしも、彼が18歳のときから栄養とトレーニングの問題に取り組んでいたとしたら、もっと素晴らしい選手になっていたことでしょう」
(生島 淳2015『ラグビー日本代表ヘッドコーチ エディー・ジョーンズとの対話 コーチングとは「信じること」』)
それから数年経ち、エディーさんの遺産を充分に活かした、日本代表の2019年W杯での活躍は今さら紹介するまでもありません。
その裏側には、数年間とは言えスポーツ栄養学の専門家も起用しての、選手たちへの知識の浸透もあったのでしょう。
ポスト・エディー世代の若い選手の意識も変わってきています。
NTTコミュニケーションズ・シャイニングアークスの金 正奎選手は、「#きんめし」とハッシュタグを付けた投稿を続けています。
最近のメニューでは「サバ缶トマト煮」。
比較的簡単に作れる、栄養バランスを考えたメニューが紹介されています。
栄養価を考えながら食事を作る・摂るのは「こんな感じなんだな」とイメージを持つ意味でも、ゆるアスにもガチアスにも参考になります。
というわけで次回に続く。