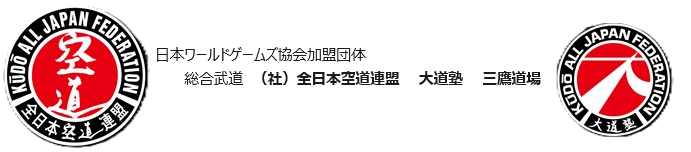20220122 KNOCK OUT-REDスーパーウェルター級 3分3R・延長1R
津崎 善郎(ライラプス東京北星ジム)
vs.
平塚 洋二郎(チーム・タイガーホーク/大道塾仙南支部)

”最先端の総合武道”空道 大道塾 三鷹同好会/Team Tiger Hawk Tokyoの小野です。
ほとぼりが冷めたころに(笑)、小野もセコンドに入った試合レポートです。
(^_^;)
今回もコーナーマンの視点から書いてみます。
前戦に続きKNOCKOUT参戦となった洋二郎。
比較的短いスパンでの再オファーは、中島戦は敗れたとはいえ一定の評価を得られた証でもあります。
平塚洋二郎と小野との関係は、前戦や以前のレポートでも触れていますので、ご興味があればご一読ください。
対する津崎。
自らもラジャダムナンスタジアムのタイトルホルダーでもある、石毛慎也会長率いるライラプス東京北星ジムの現在のエースと言ってもいいのではないでしょうか。
重いパンチとタフネスを武器にしていますが、2021年は初のKO負けを経験、前戦(偶然、洋二郎vs.中島戦と同じ興行で、ひとつ前の試合順でした)ではダウンを喫してからカットとダウンを奪い返しての逆転勝ちでした。
今回はスッキリ圧勝したいところだったでしょう。
そして、石毛さんには小野も長くお世話になっており、関係の深いキックボクサーです。
小野の古巣である大道塾吉祥寺支部には、日常的にキックボクサーの方々が練習にいらしていた時期があります。
2003年頃から数年間は、北沢勝さん、大野信一朗さん、大月晴明さん、望月竜介さん、正木和也さんなど、チャンピオンクラスの選手が毎週誰かしら練習していたと思います。
主な目的は、小野の師匠である飯村健一先生とのミットトレーニングとスパーリングで
したが、小野を含め吉祥寺支部の選手・生徒にも胸を貸してくれました。
この時期の経験は、小野のキャリアの終盤の成長に間違いなくブースター的な効果をもたらしましたし、他の後輩たちも同じだと思います。
石毛さんも、その1人です。
練習以外でも、小野の後輩で北斗旗軽量級を2度制し、プロのキックボクシングでも10年に渡るキャリアを持つ末廣智明の試合の際にセコンドを手伝っていただいたこともしばしばあり、道場ぐるみの恩人と言っても差し支えない存在です。
そんな石毛さんのお弟子さんとの試合。
...正直いろいろやりづらいなと思ったのは確かです。
(^_^;)
そして今回は、それ以上に自分のコーナーマンとしての経験値も、まだまだ足りない、石毛さんには遠く及ばないなと(当たり前ながら)痛感させられた試合でした。
試合展開を追ってみましょう。
1R、お互いにローキックの蹴り合いで様子見の立ち上がりです。
津崎はロングレンジから左ミドルも積極的に蹴ってきます。
対する洋二郎も蹴り返しますが、かわされます。
このパターンの攻防は、この試合全体を通して何度か見られましたし、こちらとしては一番の誤算でした。
最も警戒しなければならない津崎の武器は右ストレート、左フックです。
あとは組み際のヒジ打ち。
遠間の蹴りは、さほどの威力も感じないので脅威にはならないだろうと踏んでいました。
洋二郎は蹴って入るスタイルなので、この距離で闘えばリズムをつかめるはず、と。
そして、パンチを当てたい津崎は蹴りをブロックして距離を詰めるはずなので、そこにカウンターを合わせるプランを立てていました。
が、確かにさほどの重さはないものの、津崎の左ミドルはタイミングよく洋二郎を捉え、蹴り返すと距離をはずされる展開になりました。
試合後に洋二郎本人も「蹴りが当たらないので焦った」とコメントしたように、こちらとしては取れるエリアと想定していた距離でペースをつかまれてしまいました。
「焦り」「迷い」は、それとして自覚しつつ次の展開を引き出して対処しないといけないのですが、その準備が整う前に、津崎が得意の距離に踏み出してパンチをヒットさせます。
こちらの印象としては「やべっ!」でしたね。(^_^;)
本来取りたい距離でペースが取れない洋二郎は、早くも手数が落ちます。
攻撃がブロックされるのは、まだリズムをつかめますが、よけられると攻撃自体出しづらくなりますね。
しかし、いい場面もありました。
組んでの攻防はあまり得意でないだろう、というのもこちらサイドの津崎分析のひとつです。
ここは予想通り、洋二郎が組んであっさりとこかすことに成功しました。
ここは勝機を見出す大きな場面になった可能性はあるのですが、結局その
穴を潰すまでに至りませんでした。
空道は投げ技寝技も認められる”総合武道”ですので、津崎サイドからすると、組んでの展開ではもともと勝負しない想定はあったかもしれません。
そう仮定すると、ムエタイと違い、キックボクシングでは首相撲の優劣がそのまま勝敗を左右するわけではないので、リスクを取って頑張るよりは体力を温存しつつブレイクされる方がいいという判断は妥当でしょう。
試合後日、前述の末廣智明が空道の試合できれいにこかし技を決めている動画に対し、津崎が「これ平塚選手にやられた気がする」とSNSでコメントしていましたが、洋二郎はそんなに上手くありません(笑)。(^_^;)
組みの展開に持ち込むことは、この後のインターバルでも指示していましたが、なかなかその距離に入れませんでした。
それでも勝機を見いだせる展開に、強引にでも持ち込ませるべきでした。
2Rも展開は変わらず、遠間でペースを握られる洋二郎ですが、飛び込むところに合わせる狙いをみせることで、津崎もはっきりとクリーンヒットが取れない時間帯が続きます。
お互いに思い通りにはなっていない中でも、差をつけるなら津崎優位だろうという流れのまま、最終Rへ。
そこで小野が何を考えていたかと言うと。
ロングレンジで優位に立つプランは崩れた。
と言って、優位な組み際を有効活用もできていない(ヒザやヒジまでつなげられればいいのですが、崩したところでブレイクが続いたので印象的にはさほど良くはない)。
津崎もけしていいリズムとは思ってなさそう。
となると、倒しに来させてカウンターを合わせる狙いしかないかな、となりました。
3Rからでも、やはり手数を増やして組み際も勝負させたほうが、結果としては、もしかすると合わせるチャンスも増えたのかもしれません。
タラレバではあるものの、そこは采配ミスを認めるしかないかなと思います。
津崎サイドからは、ずっと「手数を増やせ」という指示が飛んでいました。
つまり。
「戦略を変えるべきビハインドの洋二郎サイドは、プランを守ることに執着」に対し「リードしている津崎サイドは、あくまで自分のスタイルで押し切ることを選択」という図式になっていました。
そのため、あまりメリハリのない試合になってしまいましたね。
しかし洋二郎も遅まきながら危ない距離に立ってパンチを当てる場面も増えてきます。
しかしやはりその距離では津崎のパワーが上回ります。
終盤、津崎のパンチがヒットして洋二郎の動きが止まるシーンもあり試合終了。
首をかしげる津崎ですが、判定は3-0で津崎です。
ポイントリードはほぼ間違いながら、自分のスタイルで倒すことを求めていたからなのでしょう。
ダウンも取れなかったことに納得できなかったということですね。
対する洋二郎も、勝負を投げずに最後までチャンスを伺う姿勢は見せてくれました。
しかし、やはりビハインド側は自分から仕掛けないとダメですし、その指示を出さなかった小野のミステイクです。
勝った津崎は来月次戦を闘います。
NKB 2022 喝采シリーズ 2nd 4/23(土) 後楽園ホールです。

師である石毛さんは元NKBのチャンピオンでした。
アウェイで強敵相手になりますが、勝ってさらに前進して欲しいものです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。