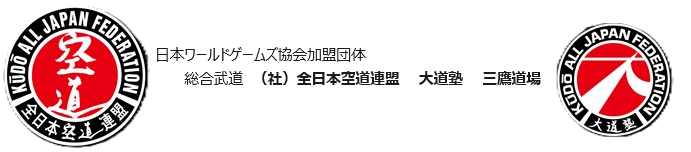”最先端の総合武道”空道 大道塾 三鷹同好会/Team Tiger Hawk Tokyoの小野です。
武道/格闘技が脳にもいい習慣じゃないかとか考えてみてます。
1. 自身の身体をコントロールする必要があり、
2. かつその身体操作のバリエーションがとても多く、
3. 対人であるため、瞬間的な判断力が求められるゲーム的要素もあり、
4. しかもまったく同じ局面は2度となく、
5. かつ、他者との協働が必要
という流れで進めていますが、今回は「2.身体操作のバリエーションの多さ」について考えてみます。
前回、スポーツ全般に言えることとして、自身の身体を意識して操作することが脳の成長を促す可能性があるのではと書きました。
今回から、数あるスポーツの中でも、武道/格闘技が優れているのではと思われることを整理してみます。
一口に武道/格闘技と言っても、世界中に数多く存在します。
例として、シンプルにナックルパート(拳の前面)のみで攻撃が許されるボクシングで考えてみましょう。
ボクシングの攻撃の技術体系は、ストレート、フック、アッパーカットの3種類に分かれます。
ある意味単純に見えますが、その3種類の攻撃でも、左と右では打ち方はまったく異なります。
身体操作レベルでは、事実上6種類のパターンになるということです。
そして、科学的な検証などはもちろんありませんが、小野の師匠である飯村健一先生は、何度もこう言われてました。
「フックは本能で打てる。ストレートとアッパーは練習しないと打てない。」
確かに、打撃系格闘技を経験したことがない人に、相手をパンチで倒せ、とムチャぶりをしたら、大ぶりのフックになると思います。
フックだって練習は必要ですが、ストレートとアッパーは練習して、つまり「脳に動きを覚えさせる」ことで打てるようになるということです。
もちろん天才と言われる人たちは別かもしれませんが。
80年代のムエタイのスター選手だったサーマート・パヤクァルンは、華麗な蹴りで相手を翻弄して、パンチでKOする試合をしてましたが、そのパンチの打ち方は、ある意味では練習で身につけたとは思えないような印象があります。
「どうやって打ったの?」と思ってしまうような。
90年代の人気ボクサー、「プリンス」ナジーム・ハメドもそうですよね。
脱線しました。(^_^;)
パンチのパターンの話に戻すと。
左のストレートであるジャブを見ると、まっすぐアゴを狙うジャブ、打ち下ろし気味に目を狙うジャブ、鞭のようにしならせて打つフリッカージャブと、打ち方のバリエーションが多く存在します。
余談ですが、最近のボクサーでジャブの打ち分けが上手いのは、「ノックアウト・ダイナマイト」内山高志ではないかと個人的に思っています。
フィニッシュシーンでは、強烈な右ストレートで対戦相手をマットに沈めていましたが、よく見ると、そこまでのプロセスでは多彩なジャブで確実に距離を制していることに気づきます。
本人も最近のインタビューで、ジャブが当たらないとストレートが当たらない、という意味の発言をしていました。

右拳を傷めて苦戦しながら、左ジャブでTKOに追い込んだ試合もありましたね。
また話がそれました(笑)。(^_^;)
左ジャブひとつ取っても、その打ち方は様々で、そのひとつひとつで異なる身体操作が必要となります。
左ジャブはバリエーションの多いパンチではありますが、他にもジャブのようにアッパーを使ったり、右ストレートとフックの間のようなオーバーハンドの打ち方もポピュラーな技術です。
左フックとアッパーの中間の打ち方、”スマッシュ”なんていうパンチもありました。
80~90年代に活躍した、ドノバン・ ”レイザー”・ラドックが得意としてましたね。
「はじめの一歩」で言うと、千堂武士のフィニッシュブローです。
小野は自身のスタイルとしては宮田君寄せのつもりですが(あんな華麗じゃないですが (^_^;))、キャラ的には千堂推しですね。
間柴了も捨てがたいですが。
...今回は脱線多いな(笑)。
ともかく、基本のパンチは3種類ですが、打ち方は数多くのバリエーションがあります。
それぞれ異なった身体操作を必要とするということは、それだけ脳のコントロールパターンが多いということになりますね。
しかも、単体でなくパンチをコンビネーションで打つことを考えると、組合せでいくつものパターンが派生してきます。
しかも、攻撃の技術体系のみで考えましたが、ここに防御技術が加わり、フットワークやボディワークが加わりとなるのですから、ボクシングをするための脳は大忙しです。
走る、泳ぐといった身体操作では、そのようなことは起こりえません。
※念のため。走るのも泳ぐのも、競技としての価値はもちろん、トレーニングとして取り入れる価値もとても高いと考えています。
パンチだけ見ても、そんなことになるのですから、蹴り技、肘打ち、膝蹴り、投げ技、抑え技、関節技、絞め技など、武道/格闘技の技術体系を考えていくと、スーパーコンピューターで計算したいくらいのパターンが必要となるはずです。
多くの球技などと比べても、身体操作パターンの複雑さと多さは圧倒的ではないでしょうか。
そう考えると、人間の脳ってすごいなと思うわけですが、もちろんすべて実現できる人なんていませんし、その必要もありません。
普段の練習の際に、いつも通りの打ち方だけではなくて、ちょっと変えてみる一工夫を入れるだけで、脳によいだけでなく、単純に試合などの結果にも影響するのではないでしょうか。
考えて練習するのと、考えないで練習するのでは、1年とか5年とかのスパンで見たときに大きな差となるはずです。
そんなところで次回に続きます。
1. 自身の身体をコントロールする必要があり、
2. かつその身体操作のバリエーションがとても多く、 ←今回
3. 対人であるため、瞬間的な判断力が求められるゲーム的要素もあり、 ←次回
4. しかもまったく同じ局面は2度となく、
5. かつ、他者との協働が必要